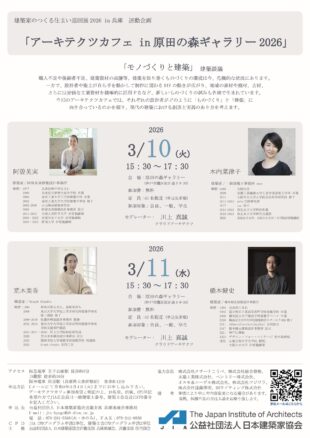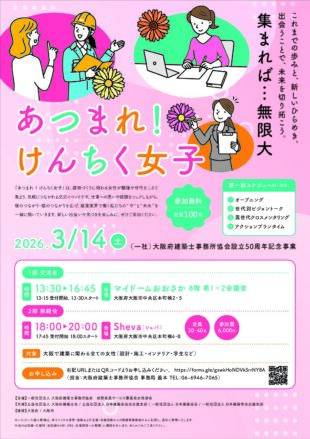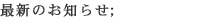2015年第1回デザイントークの報告と印象
建築デザイン研究会委員長
岩田 章吾
2015年度第1回のデザイントークは、吉永規夫さん、山口陽登さん、白須寛規さんという関西で活躍中の30代の建築家をプレゼンターに迎え、コメンテイターは石井良平さん、前田茂樹さん、松尾和生さん、矢部達也さんに岩田という構成。司会はいつものように青砥聖逸さんにお願いした。オーディエンスは会場定員の80名近くに達し、プレゼンターの活動への関心の高さが伺えた。
吉永さんの「マイナスから建築を考える」
吉永さんはデザイントーク委員でもある本多友常さんの大学、事務所両方にわたる教え子である。その影響を受けたという吉永さんは、建築を作るということの罪深さを踏まえながら、環境を常に考え設計するというスタンスを表明した。「陶器祭りの家」「くすのき階段の家」は新築であるが、周辺環境に配慮しながら、無理のない形式で丁寧に作られており、伝統的な長屋のローコスト+セルフビルドによる改修である、「ヨシナガヤ」では、古い長屋の枠組を今日的な生活空間へと再構成している。これらの建築は、本人が語るように一見「素直」で、「背伸びしない」建築と考えられがちだが、矢部さんが指摘したように、スケール感を微妙にずらすなど、意識的(あるいは戦略的な?)な「素直」さとも感じられた。一方、アートユニット「NPO」の活動は、風呂を奉った建築的山車による祝祭的な表現となっており、その表現は「意識的な素直さ」といったものではなく、より直接的な「表現」になっていたように思われる。これは吉永さんの違う面のあらわれなのだろうか?建築を作る申し訳なさと、祭りの山車という蕩尽そのものの過剰さこの二つの側面は、吉永さんのなかでどのようにバランスしているだろうか?後者が人間同士の交流や社会により直接かかわるからということだけであるならば、建築のポテンシャルを閉じることになるのではないだろうか?
山口さん、白須さんの「あたらしさ」と「あたらしさのおわり」
ともに大阪市立大学出身の山口さんと白須さんは、事務所をシェアしており、二人で設計したり単独で設計したりというゆるやかなユニットというような形で活動している。二人で設計されている「コンスタントアパートメント」「Small Hotel」、白須さんが設計されている「萩原天神の家」山口さんが設計されている「House in Tomio」それぞれアプローチが異なっていて大変興味深かった。白須さん単独のプロジェクト「萩原天神の家」は、ここ数年(十数年?)の建築雑誌をリサーチし、掲載作品に共通するデザインモチーフを「建築萌え要素」と称し、タイポロジー化、チャート化し、敷地やクライアントの要望からそれらをアッセンブルすることで建築を作ろうという試みのようだ。彼自身が語るように、「(先人から)何かを受け取ってそれを更新する」というスタンスは二人に共通するものだと思われる。しかし、このプロジェクトでは設計手法をクリエイションからアッセンブルへ更新するとうことより、その若干偽悪的なアプローチによって、もはや住宅において「新しさ」は存在しないという批評的側面を打ち出そうとしているように感じた。山口さんの「House in Tomio」は周辺に立つハウスメーカなどによる住宅が、均質なワンボリュームである点に注目し、コストというパラメーターを使い、耐久性の高い部分と低い部分に分け「あらかじめ増築されたような家」を構想している。はたしてこの戦略がコスト的にうまく機能するかは不明だが、利用形態の変容などに耐えうる空間を作っていくという姿勢には好感が持てた。この二人の個性がぶつかり合う「コンスタントアパートメント」と「Small Hotel」は、ワンルームマンション、ゲストハウスという比較的最近生まれた種類の建物のビルディングタイプの解体・更新を意図している。特に、鹿島賞を受賞した「コンスタントアパートメント」は単純な構成から多様なプランが産出できるというアイデアが秀逸だった。また、驚くべき精度で作られたこのプロジェクトの建築模型において、多様なタイプの住宅の内部には、新しいライフスタイルではなく、モノにあふれた日常的な空間が入れ込まれており、この点は、個々の空間表現には拘泥しないという彼らのスタンスを示しているといえるだろう。ただ、「Small Hotel」が利用者の快適性がビルディングタイプ解体、そしてプラン構築のためのパラメーターとなっていたのに対して、「コンスタントアパートメント」はむしろ部屋のバリエーションの多産性という点のみにパラメーターが集中していたようにも見え、それが良くも悪くもこのプロジェクトにゲーム的な軽さを与えているように思えた。個々の空間における形態やデザインは、すでに「あたらしさのおわり」を迎えていることを批評的に示しながら、ビルディングタイプの解体・更新に向かうかれらの「あたらしさ」の探求の向こうには何があるのだろうか?それはかつてのアルド・ロッシらによるタイポロジーとは明らかに異なるものとなるだろう。また、今回は、模型のみのプレゼンテーションが、より論点を先鋭化したといえるが、実際の空間を構築していく中で、彼らがどのような選択・選別を行っていくのかも大変興味がある点である。
今回、同じ世代でありながら、一見正反対の方向を向いている見える、吉永さんと白須さん+山口さんだが、いわゆる「マッチョな」建築に対する疑問といった点では共通していたように思う。会場からの質問で貴志泰正さんからの「建築における感動」という質問において、「感動」という視点で建築を語ることへのかれらの困惑ぶりが、このことを特徴付けてるなぁという印象を持った。これは、世代的なものなのだろうか?いずれにせよ、彼らの今後の活躍にさらなる興味がつのるトークセッションであった。
写真撮影:荒木義久


 関連記事
関連記事